お月見だんご
2013年09月19日
今日は、満月で十五夜さんです。
今晩は付きもきれいに見えそうなので、
おだんご作ってお月見しよう!
「お月見」の由来
お月見は、中国から平安時代の宮中に伝わった月を愛でる宴の風習。
旧暦8月15日に行われ、この頃の月を「十五夜」「中秋の名月」と呼びました。
江戸時代には庶民の行事としても定着し、秋の七草を飾り、
お団子や里芋などの季節の豊作物を備えました。
材料
上新粉 200g
さとう 20g
ぬるま湯 200ccくらい
作り方
1.耐熱のボウルに上新粉と砂糖を入れ軽く混ぜる。
ぬるま湯を注ぎ、木べらで粉っぽさがなくなるまでよく混ぜる。
ラップをして、電子レンジ500Wで3分ほど加熱する。
2.とりだし、木べらで混ぜ、もう一度、電子レンジで3分加熱する。
3.木べらでよく混ぜ、電子レンジで2分加熱する。
生地がまだやわらかければ、さらに1分ずつ加熱する。
4.すりこぎに水をつけながら、生地をつく。
5.粗熱がとれたら、ぬれぶきんにのせ、ふきんごとよくこね、
なめらかになったら、生地に手水をつけながら、耳たぶくらいのやわらかさにこねる。
6.生地をひと口大にちぎって団子状に丸め、器に盛る。
7.15個のお団子(下段8個、中段4個、上段2個、最上段1個の4段重ね)を供えます。
8.お供えした団子は、月を眺めたあと、家族みんなで食ます。
ランキングに参加しています。
ポチッと押していただけると嬉しいです
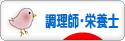
にほんブログ村
 ありがとうございました。
ありがとうございました。
今晩は付きもきれいに見えそうなので、
おだんご作ってお月見しよう!
「お月見」の由来
お月見は、中国から平安時代の宮中に伝わった月を愛でる宴の風習。
旧暦8月15日に行われ、この頃の月を「十五夜」「中秋の名月」と呼びました。
江戸時代には庶民の行事としても定着し、秋の七草を飾り、
お団子や里芋などの季節の豊作物を備えました。
材料
上新粉 200g
さとう 20g
ぬるま湯 200ccくらい
作り方
1.耐熱のボウルに上新粉と砂糖を入れ軽く混ぜる。
ぬるま湯を注ぎ、木べらで粉っぽさがなくなるまでよく混ぜる。
ラップをして、電子レンジ500Wで3分ほど加熱する。
2.とりだし、木べらで混ぜ、もう一度、電子レンジで3分加熱する。
3.木べらでよく混ぜ、電子レンジで2分加熱する。
生地がまだやわらかければ、さらに1分ずつ加熱する。
4.すりこぎに水をつけながら、生地をつく。
5.粗熱がとれたら、ぬれぶきんにのせ、ふきんごとよくこね、
なめらかになったら、生地に手水をつけながら、耳たぶくらいのやわらかさにこねる。
6.生地をひと口大にちぎって団子状に丸め、器に盛る。
7.15個のお団子(下段8個、中段4個、上段2個、最上段1個の4段重ね)を供えます。
8.お供えした団子は、月を眺めたあと、家族みんなで食ます。
ランキングに参加しています。
ポチッと押していただけると嬉しいです

にほんブログ村
 ありがとうございました。
ありがとうございました。Posted by あ~ちゃん at 18:40│Comments(0)
│お菓子レシピ










