家庭でできる食中毒予防 2
2012年07月14日
家庭でできる食中毒予防6つのポイント⇒厚生労働省
これが見やすくてわかりやすいのでいいかなーと思います。
3 下準備
・台所を見渡してみましょう。
ゴミは捨ててありますか? タオルやふきんは清潔なものと交換し てありますか?
せっけんは用意してありますか?
調理台の上は かたづけて広く使えるようになっていますか?
もう一度、チェックをしましょう。
・手を洗いましょう。
生の肉、魚、卵を取り扱った後には、また、手を洗いましょう。
途中で動物 に触ったり、トイレに行ったり、おむつを交換したり、
鼻をかんだりした後 の手洗いも大切です。
・肉や魚などの汁が、果物やサラダなど生で食べる物や
調理の済んだ食品にかからないようにしましょう。
・生の肉や魚を切った後、洗わずにその包丁やまな板で、
果物や野菜など生で食べる食品や調理の終わった食品を切ることはやめましょう。
・洗ってから熱湯をかけたのち使うことが大切です。
包丁やまな板は、肉用、魚用、野菜用と別々にそろえて、使い分けるとさらに安全です。
・ラップしてある野菜やカット野菜もよく洗いましょう。
・冷凍食品など凍結している食品を調理台に放置したまま解凍するのはやめましょう。
室温で解凍すると、食中毒菌が増える場合があります。
解凍は冷蔵庫の中や電子レンジで行いましょう。
また、水を使って解凍する場合には、気密性の容器に入れ、流水を使います。
料理に使う分だけ解凍し、解凍が終わったらすぐ調理しましょう。
解凍した食品をやっぱり使わないからといって、冷凍や解凍を繰り返すのは危険です。
冷凍や解凍を繰り返すと食中毒菌が増殖したりする場合もあります。
・包丁、食器、まな板、ふきん、たわし、スポンジなどは、使った後すぐに、
洗剤と流水で良く洗いましょう。
ふきんのよごれがひどい時には、清潔なものと交換しましょう。
漂白剤に1晩つけ込むと消毒効果があります。
包丁、食器、まな板などは、洗った後、熱湯をかけたりすると消毒効果があります。
たわしやスポンジは、煮沸すればなお確かです。
4 調理
・調理を始める前にもう一度、台所を見渡してみましょう。
下準備で台所がよごれていませんか?
タオルやふきんは乾いて清潔なものと交換しましょう。
そして、手を洗いましょう。
・加熱して調理する食品は十分に加熱しましょう。
・加熱を十分に行うことで、もし、食中毒菌がいたとしても殺すことができます。
めやすは、中心部の温度が75度Cで1分間以上加熱することです。
・料理を途中でやめてそのまま室温に放置すると、細菌が食品に付いたり、増えたりします。
途中でやめるような時は、冷蔵庫に入れましょう。
・再び調理をするときは、十分に加熱しましょう。
・電子レンジを使う場合は、電子レンジ用の容器、ふたを使い、調理時間に気を付け、
熱の伝わりにくい物は、時々かき混ぜることも必要です。
食中毒予防の三原則は、食中毒菌を「付けない、増やさない、殺す」です。
厚生労働省より
ランキングに参加しています。
ポチッと押していただけると嬉しいです
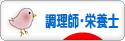
にほんブログ村
 ありがとうございました。
ありがとうございました。
これが見やすくてわかりやすいのでいいかなーと思います。
3 下準備
・台所を見渡してみましょう。
ゴミは捨ててありますか? タオルやふきんは清潔なものと交換し てありますか?
せっけんは用意してありますか?
調理台の上は かたづけて広く使えるようになっていますか?
もう一度、チェックをしましょう。
・手を洗いましょう。
生の肉、魚、卵を取り扱った後には、また、手を洗いましょう。
途中で動物 に触ったり、トイレに行ったり、おむつを交換したり、
鼻をかんだりした後 の手洗いも大切です。
・肉や魚などの汁が、果物やサラダなど生で食べる物や
調理の済んだ食品にかからないようにしましょう。
・生の肉や魚を切った後、洗わずにその包丁やまな板で、
果物や野菜など生で食べる食品や調理の終わった食品を切ることはやめましょう。
・洗ってから熱湯をかけたのち使うことが大切です。
包丁やまな板は、肉用、魚用、野菜用と別々にそろえて、使い分けるとさらに安全です。
・ラップしてある野菜やカット野菜もよく洗いましょう。
・冷凍食品など凍結している食品を調理台に放置したまま解凍するのはやめましょう。
室温で解凍すると、食中毒菌が増える場合があります。
解凍は冷蔵庫の中や電子レンジで行いましょう。
また、水を使って解凍する場合には、気密性の容器に入れ、流水を使います。
料理に使う分だけ解凍し、解凍が終わったらすぐ調理しましょう。
解凍した食品をやっぱり使わないからといって、冷凍や解凍を繰り返すのは危険です。
冷凍や解凍を繰り返すと食中毒菌が増殖したりする場合もあります。
・包丁、食器、まな板、ふきん、たわし、スポンジなどは、使った後すぐに、
洗剤と流水で良く洗いましょう。
ふきんのよごれがひどい時には、清潔なものと交換しましょう。
漂白剤に1晩つけ込むと消毒効果があります。
包丁、食器、まな板などは、洗った後、熱湯をかけたりすると消毒効果があります。
たわしやスポンジは、煮沸すればなお確かです。
4 調理
・調理を始める前にもう一度、台所を見渡してみましょう。
下準備で台所がよごれていませんか?
タオルやふきんは乾いて清潔なものと交換しましょう。
そして、手を洗いましょう。
・加熱して調理する食品は十分に加熱しましょう。
・加熱を十分に行うことで、もし、食中毒菌がいたとしても殺すことができます。
めやすは、中心部の温度が75度Cで1分間以上加熱することです。
・料理を途中でやめてそのまま室温に放置すると、細菌が食品に付いたり、増えたりします。
途中でやめるような時は、冷蔵庫に入れましょう。
・再び調理をするときは、十分に加熱しましょう。
・電子レンジを使う場合は、電子レンジ用の容器、ふたを使い、調理時間に気を付け、
熱の伝わりにくい物は、時々かき混ぜることも必要です。
食中毒予防の三原則は、食中毒菌を「付けない、増やさない、殺す」です。
厚生労働省より
ランキングに参加しています。
ポチッと押していただけると嬉しいです

にほんブログ村
 ありがとうございました。
ありがとうございました。Posted by あ~ちゃん at 18:40│Comments(0)
│からだのこと









