スポンサーサイト
きのこに注意
2010年10月19日
実りの秋です。
きのこ狩りが楽しみという方も多いと思います。
でも、毎年全国では、毒きのこによる食中毒が発生しています。
野生きのこを食べるときは、十分注意してほしいです。
食べられるきのこと確実に鑑別できないものは採らない、食べない、人にあげない。です。
食中毒:富士山ろくで採取のキノコで--平塚の一家3人 /神奈川
県食品衛生課は15日夜、富士山ろくで採ったキノコを食べた平塚市の一家3人が、食中毒になって入院したと発表した。嘔吐(おうと)や意識障害などの症状があるという。同課は「食べられるかどうか安易に判断しないで」と呼びかけている。
県によると、14日に男性(67)が山梨県側の富士山ろくでキノコを採取し、夕方に自宅でキノコ汁や天ぷらにして妻と息子の3人で食べたところ体調が悪化し、伊勢原市内の病院に救急搬送された。症状などから、毒性の強いテングタケの一種による中毒とみられる。
毎日新聞社にのってました。(記事引用しました。)
長野県が毒キノコ注意報
毒キノコによる食中毒の発生が相次いでいることから、県は13日までに全県に食中毒注意報を発令した。毒キノコによる食中毒注意報は初めて。今月8日に中野市、10日に須坂市、11日に佐久市で毒キノコのツキヨタケやクサウラベニタケを食べたことによる食中毒が連続して発生。合わせて9人が嘔吐(おうと)などの症状を示した。県内では昨年、一昨年と毒キノコによる食中毒はなく、県では短期間に連続して食中毒が発生したことを重視して初の注意報発令となった。
産経ニュースにのってました。(記事引用しました。)
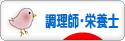
にほんブログ村
きのこ狩りが楽しみという方も多いと思います。
でも、毎年全国では、毒きのこによる食中毒が発生しています。
野生きのこを食べるときは、十分注意してほしいです。
食べられるきのこと確実に鑑別できないものは採らない、食べない、人にあげない。です。
食中毒:富士山ろくで採取のキノコで--平塚の一家3人 /神奈川
県食品衛生課は15日夜、富士山ろくで採ったキノコを食べた平塚市の一家3人が、食中毒になって入院したと発表した。嘔吐(おうと)や意識障害などの症状があるという。同課は「食べられるかどうか安易に判断しないで」と呼びかけている。
県によると、14日に男性(67)が山梨県側の富士山ろくでキノコを採取し、夕方に自宅でキノコ汁や天ぷらにして妻と息子の3人で食べたところ体調が悪化し、伊勢原市内の病院に救急搬送された。症状などから、毒性の強いテングタケの一種による中毒とみられる。
毎日新聞社にのってました。(記事引用しました。)
長野県が毒キノコ注意報
毒キノコによる食中毒の発生が相次いでいることから、県は13日までに全県に食中毒注意報を発令した。毒キノコによる食中毒注意報は初めて。今月8日に中野市、10日に須坂市、11日に佐久市で毒キノコのツキヨタケやクサウラベニタケを食べたことによる食中毒が連続して発生。合わせて9人が嘔吐(おうと)などの症状を示した。県内では昨年、一昨年と毒キノコによる食中毒はなく、県では短期間に連続して食中毒が発生したことを重視して初の注意報発令となった。
産経ニュースにのってました。(記事引用しました。)
にほんブログ村
父ちゃんの新築物語 30
2010年10月19日
測量

さて、整地の方は、造園屋さんにお任せすることになりました。
近々、縄張り・地盤改良と、イベントが目白押しなので。
社長さんには、それに間に合うようにと、お願いをしました。
一方、土地を売買するにあたっての必要な手続きその他も、同時進行で進んでいました。
叔父さんの土地の一部を譲ってもらう場合の手順は、大雑把ですが、下記の通りになるようです。
1.測量
2.分筆
3.申請
4.売買
この内、自分達で出来るのは売買ぐらい。他は、まったく知識も無く五里霧中。
と、ここでまた救世主。父ちゃんの母親情報です。
祖父が生前に土地を購入した時や、祖父の没後に土地の相続を決めた時などに、いつもお世話になっていた行政書士の先生がいるとのこと。
これは、その行政書士の先生に相談してみるのが一番。さっそく連絡してみました。
で、アポを取り。地主である叔父さんと一緒に、行政書士の先生の事務所に伺ったんです。
先生は、既に現役を引退されていたので、代わりに、測量設計事務所を紹介していただきました。
その測量設計事務所の所長さんは、土地家屋調査士and行政書士のツワモノです。
そして数日後、行政書士の先生、測量事務所の所長さん、叔父さん、父ちゃんとその母親が一堂に会し、現地で確認作業を行いました。
測量事務所の所長さんとは、この時が初対面です。とっても気さくな方で、常に笑顔な感じでした。
今の法律では、土地の分筆をする際、その元となる土地(今回の場合は、叔父さん名義の200坪の土地)についても、キッチリと測量する必要があるそうです。
さらに、元となる土地に隣接する土地の地主さん全員に、立ち会ってもらう必要があるそうです。
地主さんが立ち会う理由は、境界線の確認・確定。
叔父さんの土地と隣接する土地の境界線に関して、不服が無ければ『立会証明書』に署名捺印して頂くことになります。
隣接する土地の地主さん全員の署名捺印が無ければ、分筆することが出来ないんです。
ここで疑問。
分筆する土地の大きさには関係しない元の土地の大きさまで、なせ測量する必要があるのか?
また、分筆する予定の土地は、他の地主さんの土地には一切接触しないんです。それなのに、なぜ立ち会いが必要なのか?
それは、こんな理由のようです。
何年も前に登記された土地の場合、登記されている土地の大きさと、実際の土地の大きさが異なっていることがよくあるらしく。
そんなテキトーな登記のままでは、境界線トラブルも後を絶たないことでしょう。
なので、この様な機会(分筆など)に、キッチリと測量をし、登記との誤差や境界線問題を解消していきたいようです。
もちろん、そんなテキトーな登記を許してきた法務局に責任があることなのでしょうが、実際は、その測量と手続きを行うのは、民間の事務所。
さらに、その経費を支払うのは、依頼主である善良な市民なんです。
『何だかな~』と思いますね。
とは言え。当時は知識も乏しく、測量事務所の所長さんの言われるがままに動いていましたので。まったく疑問には思いませんでした。
『何だかな~』と思ったのは、測量や申請などの全ての手続きが終わって、その請求書を目の当たりにした時なんですけどね・・・。
さて、そんな事情で。関係者が一堂に会したその日、膳は急げと、さっそく周辺の地主さんに立ち会いをお願いしました。
署名捺印が必要な地主さんは、全部で4名です。もちろん、本人様の署名捺印が必要です。
その日は、2名の地主さんに境界線を確認して頂き、署名捺印をして頂きました。
皆さん、境界線に関しては納得して頂いていて、スムーズに話が進みました。
測量事務所の所長さん曰く、「境界線に納得しなかったり、所在が解らない地主さんがいると、もの凄く苦労する」のだそうです。
所長さんが手掛けている別の案件で、地主さんの所在が不明な為、手続きが半年も滞っているものがあると聞きました。
その点では、ウチの周辺の地主さんは、みなさんご近所の方ばかりで。しかも、みなさん良い方ばかりなので、助かりました。
何といっても、家を建てるという事は『ここに一生住みます!』宣言をしたようなもの。
ご近所さんとのお付き合い、特に、地主さんとの関係はものスゴク大切ですからね。
さて、測量事務所の所長さんと初めて会ったその日は、2名の地主さんに署名捺印を頂いて終了です。
我らが叔父さんは、とっても忙しい人なので、そうそう来てもらうことは出来ません。
(ちなみに叔父さんは、この土地から車で1時間ほどの距離に住んでいます。)
これ以後、父ちゃんは、地主(叔父さん)の代理人として、測量事務所の所長さんと頻繁に接触し、行動を共にしました。
その時々のお話しや出会いなどの経験は、とっても勉強になったんです。
期間的には、ホンの二ヶ月ほどでしたが。
『濃い時間だったな~』と、思っています。

にほんブログ村
さて、整地の方は、造園屋さんにお任せすることになりました。
近々、縄張り・地盤改良と、イベントが目白押しなので。
社長さんには、それに間に合うようにと、お願いをしました。
一方、土地を売買するにあたっての必要な手続きその他も、同時進行で進んでいました。
叔父さんの土地の一部を譲ってもらう場合の手順は、大雑把ですが、下記の通りになるようです。
1.測量
2.分筆
3.申請
4.売買
この内、自分達で出来るのは売買ぐらい。他は、まったく知識も無く五里霧中。
と、ここでまた救世主。父ちゃんの母親情報です。
祖父が生前に土地を購入した時や、祖父の没後に土地の相続を決めた時などに、いつもお世話になっていた行政書士の先生がいるとのこと。
これは、その行政書士の先生に相談してみるのが一番。さっそく連絡してみました。
で、アポを取り。地主である叔父さんと一緒に、行政書士の先生の事務所に伺ったんです。
先生は、既に現役を引退されていたので、代わりに、測量設計事務所を紹介していただきました。
その測量設計事務所の所長さんは、土地家屋調査士and行政書士のツワモノです。
そして数日後、行政書士の先生、測量事務所の所長さん、叔父さん、父ちゃんとその母親が一堂に会し、現地で確認作業を行いました。
測量事務所の所長さんとは、この時が初対面です。とっても気さくな方で、常に笑顔な感じでした。
今の法律では、土地の分筆をする際、その元となる土地(今回の場合は、叔父さん名義の200坪の土地)についても、キッチリと測量する必要があるそうです。
さらに、元となる土地に隣接する土地の地主さん全員に、立ち会ってもらう必要があるそうです。
地主さんが立ち会う理由は、境界線の確認・確定。
叔父さんの土地と隣接する土地の境界線に関して、不服が無ければ『立会証明書』に署名捺印して頂くことになります。
隣接する土地の地主さん全員の署名捺印が無ければ、分筆することが出来ないんです。
ここで疑問。
分筆する土地の大きさには関係しない元の土地の大きさまで、なせ測量する必要があるのか?
また、分筆する予定の土地は、他の地主さんの土地には一切接触しないんです。それなのに、なぜ立ち会いが必要なのか?
それは、こんな理由のようです。
何年も前に登記された土地の場合、登記されている土地の大きさと、実際の土地の大きさが異なっていることがよくあるらしく。
そんなテキトーな登記のままでは、境界線トラブルも後を絶たないことでしょう。
なので、この様な機会(分筆など)に、キッチリと測量をし、登記との誤差や境界線問題を解消していきたいようです。
もちろん、そんなテキトーな登記を許してきた法務局に責任があることなのでしょうが、実際は、その測量と手続きを行うのは、民間の事務所。
さらに、その経費を支払うのは、依頼主である善良な市民なんです。
『何だかな~』と思いますね。
とは言え。当時は知識も乏しく、測量事務所の所長さんの言われるがままに動いていましたので。まったく疑問には思いませんでした。
『何だかな~』と思ったのは、測量や申請などの全ての手続きが終わって、その請求書を目の当たりにした時なんですけどね・・・。
さて、そんな事情で。関係者が一堂に会したその日、膳は急げと、さっそく周辺の地主さんに立ち会いをお願いしました。
署名捺印が必要な地主さんは、全部で4名です。もちろん、本人様の署名捺印が必要です。
その日は、2名の地主さんに境界線を確認して頂き、署名捺印をして頂きました。
皆さん、境界線に関しては納得して頂いていて、スムーズに話が進みました。
測量事務所の所長さん曰く、「境界線に納得しなかったり、所在が解らない地主さんがいると、もの凄く苦労する」のだそうです。
所長さんが手掛けている別の案件で、地主さんの所在が不明な為、手続きが半年も滞っているものがあると聞きました。
その点では、ウチの周辺の地主さんは、みなさんご近所の方ばかりで。しかも、みなさん良い方ばかりなので、助かりました。
何といっても、家を建てるという事は『ここに一生住みます!』宣言をしたようなもの。
ご近所さんとのお付き合い、特に、地主さんとの関係はものスゴク大切ですからね。
さて、測量事務所の所長さんと初めて会ったその日は、2名の地主さんに署名捺印を頂いて終了です。
我らが叔父さんは、とっても忙しい人なので、そうそう来てもらうことは出来ません。
(ちなみに叔父さんは、この土地から車で1時間ほどの距離に住んでいます。)
これ以後、父ちゃんは、地主(叔父さん)の代理人として、測量事務所の所長さんと頻繁に接触し、行動を共にしました。
その時々のお話しや出会いなどの経験は、とっても勉強になったんです。
期間的には、ホンの二ヶ月ほどでしたが。
『濃い時間だったな~』と、思っています。
にほんブログ村




