スポンサーサイト
食事時間がダイエットの決め手? のニュース
2012年11月14日
食事時間がダイエットの決め手?
2012.11.13, EurekAlert より:
同じものを食べていても、食事をする時間が変わるだけで肥満になりやすくなること、
また末梢組織にある体内時計の狂いが脳の視床下部にも影響を与え、
概日リズムを乱れさせるという知見が『ネイチャー医学』誌に発表された。
脂肪細胞は過剰なエネルギーを蓄え、またエネルギーが過剰にあることを
脳へ知らせるために信号を送る働きがあるが、今回、研究者らは、
脂肪細胞で発現する時計遺伝子のArntlが欠損したマウスでは、
食事時間が夜行性動物が通常食事を取る時間でない時間帯にシフトし、
脂肪細胞へのエネルギーの蓄積が亢進して、肥満になりやすくなることを明らかにした。
この発見はヒトにおける肥満の原因の解明を一歩前進させるものだということだ。
この研究の発見は、ふたつあると研究者は言う。
ひとつは、食事時間が相対的にわずかにずれて、
通常は休息している時間に食事を摂るようになるだけで、
エネルギーが蓄積されやすくなり、通常より多くのカロリーを摂取していないにも関わらず
肥満になったこと。
これは、食事時間をずらされた遺伝子が正常なマウスで肥満が増加した知見と
一致するという。
また、この食事時間の変更というマウスの行動変化はヒトにおける夜食症候群に
似ており、この夜食症候群の患者も肥満傾向を示すということである。
ふたつめの発見は、時計遺伝子そのものと関係がある。
従来、末梢組織にある体内時計は脳の視床下部にある視交叉上核(SCN)にある
マスタークロックに従って動くものであり、末梢組織の体内時計には
多少の自主性のみしかないと考えられていた。
ところが、今回の結果は、その末梢組織である脂肪細胞の時計遺伝子の欠損が、
摂食行動という明らかに中枢性の行動にまで変化を及ぼすことを示唆するものだった。
「例えるなら、打楽器奏者が指揮者の指示なしにドラムを叩いていたら、
いつのまにかそれが指揮者にも影響を与えて、
全体の動作(代謝パターン)を打楽器奏者が動かしているような状態になったようなものだ」
と研究者は語っている。
これらの発見は、代謝を調節する体内時計の重要性と、
摂食行動およびエネルギー消費において脂肪細胞が果たしている役割の重要性を
強調するものであると研究者は結論付けている。
出典は『ネイチャー医学』。 (論文要旨)
だそうです。
最近時間栄養学っていろいろ研究されてますよね。
体の中には、5種類の体内時計があるといわれています。
・週周リズム
・日周リズム(サーカディアンリズム)
・月周リズム
・年周リズム(季節性リズム)
・90分リズム(ウルトラディアンリズム)
日中活動し、夜眠る。
朝日を浴びて朝食を食べる。
夕食は夜9時くらいまでにすませる。
規則的に生活することで、カラダの機能は、
ベストコンディションに保たれるよう調節されているそう。
やっぱりそれが、健康生活の基本なんですね。
ランキングに参加しています。
ポチッと押していただけると嬉しいです
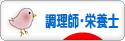
にほんブログ村
 ありがとうございました。
ありがとうございました。
2012.11.13, EurekAlert より:
同じものを食べていても、食事をする時間が変わるだけで肥満になりやすくなること、
また末梢組織にある体内時計の狂いが脳の視床下部にも影響を与え、
概日リズムを乱れさせるという知見が『ネイチャー医学』誌に発表された。
脂肪細胞は過剰なエネルギーを蓄え、またエネルギーが過剰にあることを
脳へ知らせるために信号を送る働きがあるが、今回、研究者らは、
脂肪細胞で発現する時計遺伝子のArntlが欠損したマウスでは、
食事時間が夜行性動物が通常食事を取る時間でない時間帯にシフトし、
脂肪細胞へのエネルギーの蓄積が亢進して、肥満になりやすくなることを明らかにした。
この発見はヒトにおける肥満の原因の解明を一歩前進させるものだということだ。
この研究の発見は、ふたつあると研究者は言う。
ひとつは、食事時間が相対的にわずかにずれて、
通常は休息している時間に食事を摂るようになるだけで、
エネルギーが蓄積されやすくなり、通常より多くのカロリーを摂取していないにも関わらず
肥満になったこと。
これは、食事時間をずらされた遺伝子が正常なマウスで肥満が増加した知見と
一致するという。
また、この食事時間の変更というマウスの行動変化はヒトにおける夜食症候群に
似ており、この夜食症候群の患者も肥満傾向を示すということである。
ふたつめの発見は、時計遺伝子そのものと関係がある。
従来、末梢組織にある体内時計は脳の視床下部にある視交叉上核(SCN)にある
マスタークロックに従って動くものであり、末梢組織の体内時計には
多少の自主性のみしかないと考えられていた。
ところが、今回の結果は、その末梢組織である脂肪細胞の時計遺伝子の欠損が、
摂食行動という明らかに中枢性の行動にまで変化を及ぼすことを示唆するものだった。
「例えるなら、打楽器奏者が指揮者の指示なしにドラムを叩いていたら、
いつのまにかそれが指揮者にも影響を与えて、
全体の動作(代謝パターン)を打楽器奏者が動かしているような状態になったようなものだ」
と研究者は語っている。
これらの発見は、代謝を調節する体内時計の重要性と、
摂食行動およびエネルギー消費において脂肪細胞が果たしている役割の重要性を
強調するものであると研究者は結論付けている。
出典は『ネイチャー医学』。 (論文要旨)
だそうです。
最近時間栄養学っていろいろ研究されてますよね。
体の中には、5種類の体内時計があるといわれています。
・週周リズム
・日周リズム(サーカディアンリズム)
・月周リズム
・年周リズム(季節性リズム)
・90分リズム(ウルトラディアンリズム)
日中活動し、夜眠る。
朝日を浴びて朝食を食べる。
夕食は夜9時くらいまでにすませる。
規則的に生活することで、カラダの機能は、
ベストコンディションに保たれるよう調節されているそう。
やっぱりそれが、健康生活の基本なんですね。
ランキングに参加しています。
ポチッと押していただけると嬉しいです

にほんブログ村
 ありがとうございました。
ありがとうございました。



